2024年、京都市内のある小学校で起きた深刻ないじめ事件。
小学4年生の男子児童が同級生から暴行を受け、難聴を発症し、ついには不登校、転校を余儀なくされました。
学校側の初動対応の遅れがこの事態をさらに悪化させた背景には何があったのでしょうか?
当記事では、事件の詳細と共に、保護者・教育現場が持つべき視点を探ります。
事件の経緯といじめの内容
2024年9月、男子児童は担任教員の指示で他の児童に勉強を教えたことをきっかけに、複数の同級生から暴力や暴言の対象となりはじめました。
同年11月、廊下で後ろから首を絞められ、耳の付近を3発殴られるという暴行を受け、その結果「外傷性の感音難聴」と診断されました。
男子児童は、教師に相談しても取り合ってもらえず、暴力を受けることが日常化していたと証言しています。
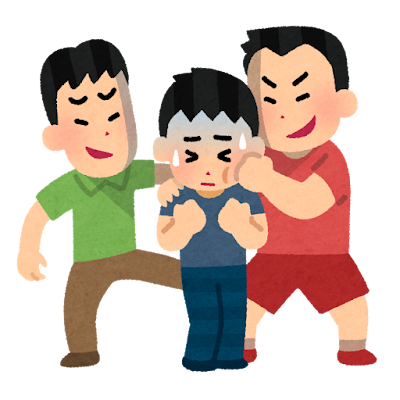
学校の対応の問題点
男子児童の母親は事件後すぐに学校や教育委員会に報告し、「いじめの重大事態」として対応を求めました。
しかし、加害児童の暴行否定や証拠の不在を理由に、学校は事態を重大と認めず、調査も遅れました。
「証拠がない」「他の児童が傷つく」などの理由で、当初はいじめの存在自体が否定されたのです。
結果的に、加害児童の証言が得られた2025年3月まで、正式な「重大事態」認定はされませんでした。
親の苦悩と後悔
事件直後、児童は「お母さんに言うのが怖かった」と語り、耳の異常をしばらくの間隠していました。
母親もまた、「早期治療の必要性を知らなかった」とし、診察が遅れたことを後悔しています。
難聴はもはや治らないと医師に宣告され、家族にとっては取り返しのつかない傷となりました。

法的視点と専門家の意見
元検事・弁護士の亀井正貴氏は、「長期欠席という重大事態があるにも関わらず、対策が不十分だった」と厳しく指摘。
被害児童の声に耳を傾け、迅速かつ客観的な調査を行うことの重要性を強調しました。
また、いじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」認定の運用が、現場では適切に行われていなかった可能性もあります。
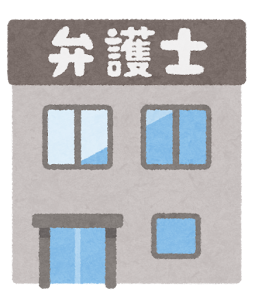
私たちに出来ること
1.子供の異変に早期に気づく感度を持つこと
耳鳴りや無気力、登校渋りなどのサインを見逃さない。
2.記録と証拠を残す習慣を
日記や写真、会話の記録が後の証明に役立ちます。
3.第三者機関や教育委員会との連携を強化する
学校内で解決が困難な場合は、早めに外部相談を活用しましょう。
ネット上での反応と声
ネット上では、
・「京都市の対応が遅すぎる」
・「40件目の重大事態なのに学ばないのか」
など、教育委員会や学校に対する批判の声が多く見られました。
また、保護者からは、
・「自分の子が同じ立場になったらと考えると怖い」
とのコメントもあり、今回の事件は多くの家庭に衝撃を与えています。

まとめ
この事件は、たった1人の児童が訴え続けても、学校と教育委員会の制度がそれに応えられなかった現実を映しています。
大人には、子供の声を真剣に受け止め、見逃さず、放置せず、寄り添う姿勢が求められています。
教育の安全性と信頼回復のために、今後の調査と改革に注目が集まることでしょう。
当記事は以上となります。


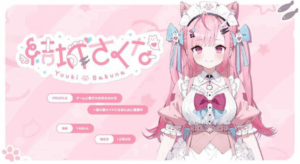

コメント